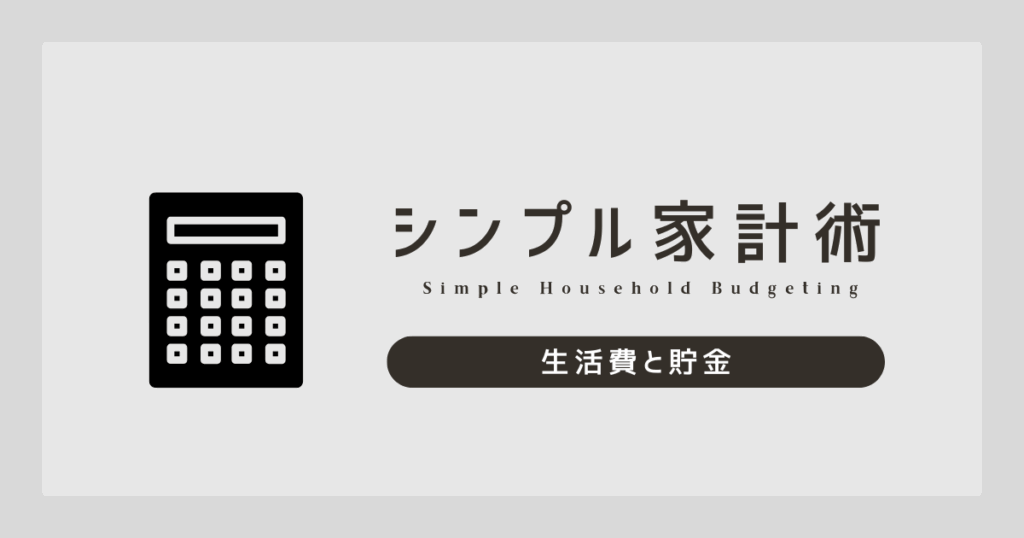
以前の記事で書いた通り、うちの夫は家計管理をまるっと私に任せちゃってます。
つまり「家計は妻におまかせ」スタイル。
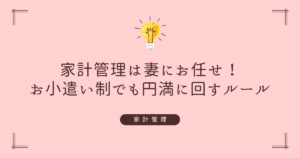
きっと同じような家庭も多いのではないでしょうか。
私はお金の管理は任されたいタイプなので、喜んで取り組んでいます。
今回は、そんな私が実際にどんなふうに家計を管理しているのか、リアルにお話ししてみます。
家計簿を始めたきっかけとやめた理由
結婚して夫と一緒に生活を始めたとき、まず気になったのは、
「一か月にどれくらい生活費がかかるのか」
ということでした。
結婚するまで実家暮らしだった私は、1カ月の生活費がどれくらい必要なのか分からなかったので、結婚を機に家計簿をつけてみようと思ったのです。
10年以上も前の話なので、まだ家計簿アプリなどが身近ではなく、ノートに手書きで記入していました。
その頃は、経理魂に火が付き、家計簿と現金残高を突き合わせて、だいたい一致していたら「よし、うまくいった!」とちょっとした達成感を味わっていました。
※まぁ、完全一致は難しいので、差額は「雑損失」「雑益」ととらえていました
けれども、その楽しさも長くは続かず、家計簿と現金残高の確認は数か月すると飽きてしまいました。
家計簿もノートに毎日記入する作業がだんだん面倒になり、結局2,3年しか続けることができませんでした。
とはいえ、家計簿をつけたことで大体どれくらいのお金が必要か、生活費の感覚をつかむことができたので、役目は果たしてくれたと思います。
私が続けているシンプルな家計管理術
その後は家計簿をやめ、よりシンプルな方法でお金を管理するようになりました。
私の家計管理の基本は「貯金を先に抜いてしまう」というやり方です。
※王道ですね
ライフステージに合わせて毎月の貯金額を決め、まずはその金額を家計用の口座から別の貯金用口座に移します。
残った金額を生活費として使うのです。
生活費には家賃、水道光熱費、通信費、保険料などの引き落としに加え、食費や日用品の購入費が含まれます。
これらをすべて、先取り貯金をした後に残ったお金でやりくりします。
生活費が余ったときには、そのまま家計用の通帳に戻すようにしています。
そうすると少しずつ余剰金が積み重なり、自然と生活費の口座にゆとりが生まれていきます。
この仕組みのおかげで、貯金用に回したお金をいままで一度も取り崩したことがありません。
生活費口座に余裕があるため、突発的な出費があってもそこから対応できるのです。
もちろん、今後は子どもの進学や進級などで大きな支出が増えていくと思うので、貯金を取り崩す場面も出てくるでしょう。ただ、これまで積み重ねてきたお金があるという安心感はとても大きいと感じています。
ポイントは、「貯金額」を臨機応変に変えていくことです。
来月は引き落としが多いから貯金額は少なめにしよう、今月はゆとりがあるから貯金額を多めにしよう、などなど。
「貯金額」の基本額は決めているけど、あまりギチギチにその額にとらわれないことが大事です!
家計簿なしでも安心できる理由
家計簿をやめても、こうした「先取り貯金」と「残った生活費でやりくり」というシンプルなルールを守るだけで、無理なく貯金を続けることができています。
細かい収支をすべて記録することにストレスを感じる人は多いと思いますが、自分に合った方法で管理できれば十分だと思います。
大切なのは続けられる仕組みをつくること。
そして、生活の変化に合わせて柔軟に見直すことだと実感しています。
結婚当初につけた家計簿は数年でやめてしまいましたが、その経験があったからこそ、今のシンプルな家計管理にたどり着けたのだと思います。
「自分の生活費の感覚をつかむため」に短期間だけでも家計簿をやってみる価値はアリです。
これからも家族の成長やライフステージの変化に合わせて、無理のない方法で家計を守っていきたいと思います。
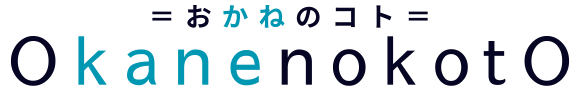
コメント